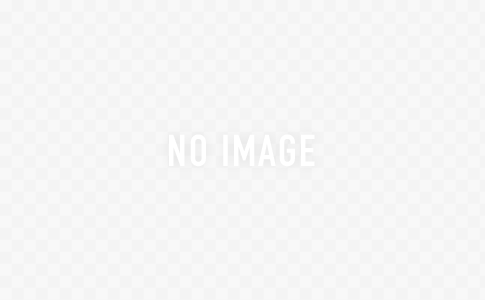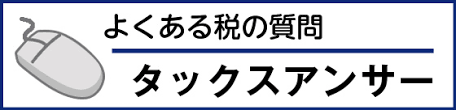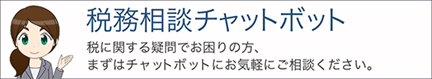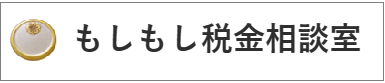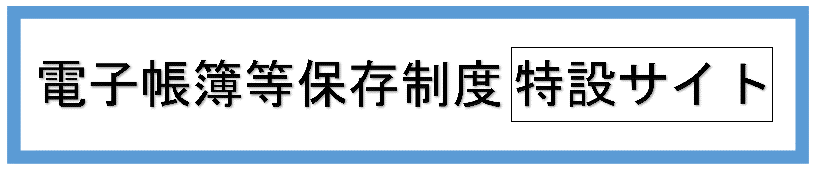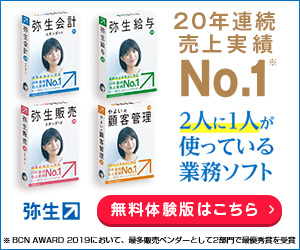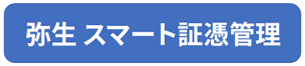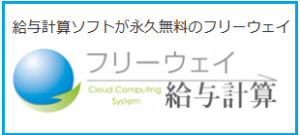国税庁は、同庁ホームページにおいて、延納許可限度額の計算方法の見直しを掲載しております。
それによりますと、令和7年度税制改正における延納許可限度額の計算方法の改正点(改正の概要)では、当面の事業経費の算出方法として、前年の事業経費の額に1/12を乗じた額として差し支えないとしていたところ、前年の事業経費の額の3/12を乗じた額として差し支えないことが挙がっております。
適用開始時期は、相続税が令和7年4月1日以後相続開始に係る延納申請及び物納申請から適用、贈与税が令和7年6月24日以後に申請期限が到来する延納申請書から適用されております。
ご利用になる方は、同庁ホームページにおいて、具体的な延納許可限度額の計算方法(改正後)が掲載されており、実際の計算に当たっては、延納申請書の別紙「金銭納付を困難とする理由書」に金額等を記入して計算することや、計算の根拠となった資料等の写しを「金銭納付を困難とする理由書」に添付する旨も掲載されておりますので、あわせてご確認ください。
また、国税庁からの注意事項として、国税は、金銭で一時に納付が原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を納期限又は納付すべき日までに、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めること(延納)ができます(延納期間中は利子税がかかる)。
そして、延納が許可されるためには、担保が
①不動産、上場株式等の有価証券、保証人による保証等であること(可能な限り処分が容易であって、かつ、価額の変動の恐れが少ないものから選択)
②担保として不適格な事由がないこと(共同相続人間で所有権を争っているもの、売却できる見込みのないもの、共有財産の持分等)
③必要担保額(延納税額及び利子税額3回分)を充足していることが必要
財産の状況・権利関係等を十分に踏まえて延納担保とする財産を選定する旨の掲載がありますので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。