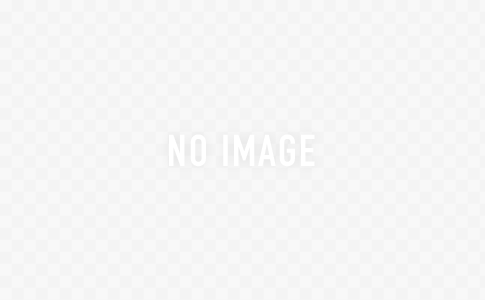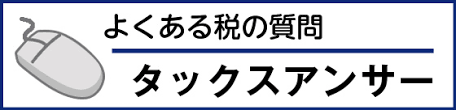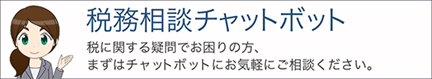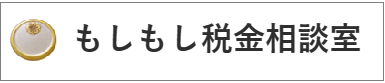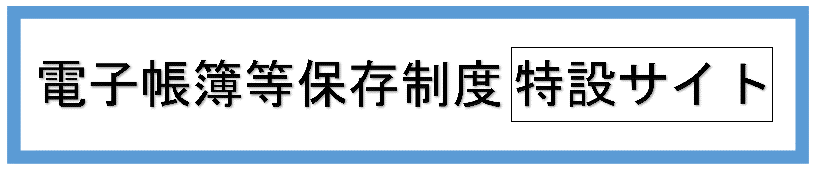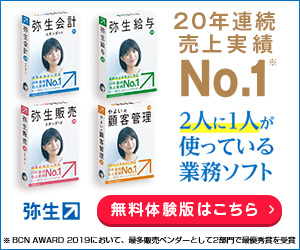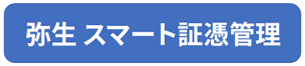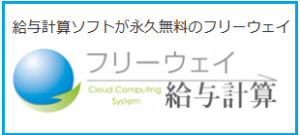国税庁は、同庁ホームページにおいて、物納許可限度額等の計算方法の見直し(令和7年4月1日以後相続開始に係る申請分から適用)を掲載しております。
それによりますと、令和7年度税制改正における物納許可限度額の計算方法の改正点(改正の概要)として、
①延納によって納付することができる金額の計算について、納期限又は納付すべき日における収入金額を基に算出していたところ、将来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法を明確化した
②延納によって納付することができる金額の計算について、年間納付資力に乗ずる年数を、一律に延納可能最長年数としていたところ、課税相続財産の種類における延納年数や平均余命年数を考慮した計算方法にした
③改正前の物納許可限度額に、延納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を加算した額を、改正後の物納許可限度額とすることが挙がっております。
ご利用になる方は、具体的な物納許可限度額の計算方法(改正後)が掲載されておりますので、ご確認ください。
また、国税庁からの注意事項として、国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限まで又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として、「物納申請書」及び「物納手続関係書類」を納期限又は納付すべき日までに、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出することにより、一定の相続財産で納付すること(物納)が認められています。
なお、物納に充てようとする財産を選択する際には、要件に該当していることが必要であり、特に、管理処分不適格財産、物納劣後財産に該当していないことを確認する必要があります。
物納に充てる財産の整備や必要書類の作成のための費用及び物納が許可されるまでの維持管理費用は、申請者ご自身の負担になります。
また、物納の許可による納付があったとされる日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納にあたっての措置を行う期間について、利子税がかかる旨も掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。